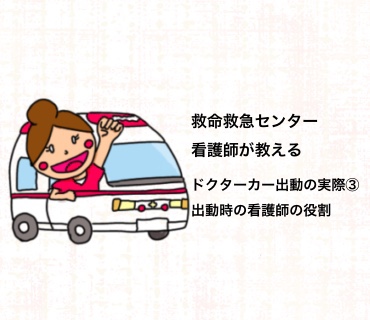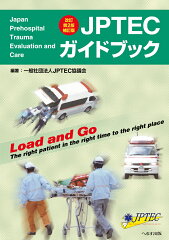こんにちはCAMP GEAR TOKYOです。

目次
はじめに
私は救命救急センターで看護師をしています。
資格では救急救命士と日本DMATも取得しています。
救命救急センター内の業務としてドクターカーへの乗車を日常的にしています。
そんな業務に興味のある方や
これからドクターカーに乗ってみたいなって思ってらっしゃる人の
情報源の一つになれればいいなと思ってこの記事を書いています。
良かったら最後まで見ていただけると嬉しいです。
今回はドクターカー同乗時の看護師の役割と病院前救急活動についてを少し語りたいと思っています。
ドクターカーの業務などに関しては過去のブログのリンクを貼っておきますのでお時間のある方はぜひ見ていただけたら嬉しいです。
過去ブログ
参考図書を一応載せておきますね。
|
|
|
|
![]()
ドクターカーの業務について
ドクターカーの業務は多岐にわたりますが、看護師としての業務に関しては
病院前のドクターカー業務でも救命救急センターの初療室
でもあまり変わりはありません。
看護師の業務は診療の補助業務と療養上の世話の業務に分かれますが
病院前の救急看護の中では圧倒的に診療の補助業務が大きな割合を占めます。
実際の出動
私が勤める救命救急センターではあらかじめドクターカー担当者を決めて置いて、担当者はドクターカー要請のチャイムや合図がなると同時に出動の準備を行って出動することになっています。
出動時に持って行く物
- 薬剤バッグ…筋弛緩薬や鎮静剤、循環作動薬などが入っています。
- 外傷バッグ…胸腔ドレーンやメス、ガーゼなどが入っています。
- ビデオ喉頭鏡…気管挿管時に必要となるビデオ喉頭鏡です。
その他の物品に関しては
ドクターカーの中にありますので、症例に応じて準備します。
出動までの時間は要請から2分ほどで出動します。
この2分が早いのか遅いのかはわかりません。
出動時の感染防御
出動時には感染防御も行います。
- ゴーグル
- ヘルメット
- マスク→COVID-19が流行してからは全症例N95マスクを行います。
- ガウン
- 反射ベスト
- 手袋
- 安全靴
です。
ここまでくるともう見た目にはだれかわかりません笑。

この時点でだいたいドクターカーは出発します。
ドクターカー車内での準備
ドクターカーは信じられないくらい揺れます。
普通の救急車はだいたいトヨタのエルグランドを救急車用にしたりしているのであまり揺れは少ないですし、救急隊の人は実は道路状況もしっかりと把握していて、段差やマンホールなどをなるべく避けながら運転しているそうです。
しかしドクターカーはトラックを改造しているため、後部の荷台部分の当センターのドクターカーは非常に揺れます。
大型バスに乗ったことって誰でもありますよね。
あの後ろの方の座席と同じくらいか、それ以上に揺れますので
走行中の作業はかなり危険を伴いますので基本的にはしません。
輸液ルートを作成したりするぐらいの事が多いです。
車内では医師と活動方針の確認を行います。
車内では現場到着した救急隊からの電話があることがほとんどです。
もう一度出動までの流れをおさらいすると
- 事案が起こって発見者が消防へ電話した時点でキーワードによるドクターカー要請
- ドクターカー担当者が準備を行い出動
- ドクターカー車内で、実際に到着した現場救急隊からの現場状況の電話を受ける
流れになっています。
ここからは2パターンあります。
- 現場救急隊が到着した結果、事案が覚知の状況と異なることがわかりドクターカーの出動がキャンセルになる事
- 現場救急隊が到着した結果、事案の詳細がわかり、詳しい状況の情報が得られる場合
です。
1の場合にはそのまま病院へ帰還します。
2の場合にはそのまま現場に向かうことになります。
現場到着
現場に到着するとまずは安全確認を行います。
安全確認は
- 自身(self)
- 現場(scene)
- 生存者(suvivor)
で行います。
まずは自分自身の安全が本当に大事で
交通整理が十分に行われていない道路
片方の電車が運航中の線路
刃物がたくさんある工場
などたくさんの危険な現場があります。
私の経験ですが、ドクターカーから降りた瞬間に
酔った患者さんの家族に胸ぐらをつかまれて
「早く助けろや!」と言われたこともあります。
とにかく自身の安全と現場の安全を確認して活動を開始します。
現場に到着すると、多くの場合では、先着の消防隊や救急隊から情報を得ることができます。
病院前現場での看護師の役割
現場での看護師の役割について言及されている文献を見たはありませんが、長年の経験として述べさせていただきます。
救急現場というのはクリティカルな場面と表現されると思います。
院内におけるクリティカルよりももっと早期のクリティカルな場面であると思われます。
クリティカルな場面での危機理論としてフィンクの危機モデルを用いることが多いと思われますが、フィンクの危機モデルは脊髄損傷の患者を対象として研究されている背景があるため、病院前救急現場における危機理論として正しいのは疑問が残ります。
2011年に山勢先生が発表されている、「クリティカルケアにおけるアギュララの問題解決型危機モデルを用いた家族看護」の中で、クリティカルな場面では患者自身と家族の危機理論としてアギュララの問題解決型危機モデルを使用しやすいことを述べられています。
アギュララの提唱する危機のプロセス
アギュララの提唱する危機のプロセス
危機を招いた出来事に遭遇→均衡状態の揺らぎ→心理的な不均衡状態→均衡回復への切実なニード→バランス保持要因の存在→不均衡状チアからの回復(危機の回避)、または不均衡状態の持続
というものであります。
つまり何かの事故などに遭遇した患者さんは、心理的な不均衡状態であるといえるのです。
当たり前のことをまわりくどく説明しましたが、ここの部分は重要だと思います。
看護師にとって患者さんがどのように感じているのかを考えることは重要なことですよね。
ではどのような援助が必要なのでしょうか。
どのような看護介入が必要か
- 安全安心のニード
- 痛みへのニード
- 不安へのニード
- 接近のニード
- 情報のニード
などがあげられるとおもいます。
安全を提供することは非常に重要です。
安全でなくても誰かがそばにいることで安心感が少しは得られるのではないでしょうか?なので私はいつも「そばに居ますよ。」と必ず声をかけ、タッチングを使用します。
痛みへは、単純に「痛みはありませんか?」と聞く、もしくは痛みがあるように他覚的に感じ取れるときにはなるべく早期に鎮痛の処置が行えるように医師と協議します。
接近のニードってややこしいですけど
何か、あったら「家族にあいたい」「大切な人に会いたい」と思いませんか?
思う人と思わない人がいると思ます。すべての人がそうだとは思いませんが、なるべく家族の方と連絡が取れていることを告げたり、そばに居ていただいたりすることが多いです。同様に家族の方も接近のニードは強くなりますので意識して行動しています。
情報のニードも重要です。
救急の現場では患者自身の情報のニードが置き去りになって診療行為が始まってしまう事があり得ますので、そういったことがないように、これから行う処置などの説明やどのような流れになるのかを伝えます。もちろん、最初に患者さんや家族の方と接触するときには自己紹介を必ず行います。
どうでしょうか?
まとめ
看護師の役割について説明しましたが
あまり一般の方には馴染みにくくイメージしずらい内容ですよね。
簡単にいうと病院で行っていることをそのまま意識して病院の外でも行っているんです。
そしてよりクリティカルな状況であるから、安心安全、情報や接近のニードが強いと感じています。
あまり面白い内容になっていなくて自分でもびっくりしていますが
実際はこのような感じです。
今度は現場に到着してから病院に帰還するまでの流れや
テクニックなども説明できたらいいのかなと思っています。
他にも
発達障害の持つ新人看護師への指導シリーズなどもありますのでよかったらみてください。
👇発達障害をもつ新人看護師の指導のブログのリンク👇
発達障害をもつ新人看護師の指導⑤発達障害に気づく、気づいてもらう